(公財)喝破道場
喝 破 五 訓
よろこんで与える人間となろう
-----------------------
命を大切にする人間となろう
-----------------------
心静かに考える人間となろう
-----------------------
使命に生きる人間となろう
-----------------------
規律ある幸せ喜ぶ人間となろう
-----------------------

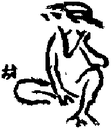
喝破だより 2010年9月号

「すべてを受容する」
―生かされていることの感謝―
茨城県の水戸市で開催された研修会に参加させて頂き、高萩市の草間吉夫市長さん(以後吉夫さん)の講演を拝聴させて頂きました。吉夫さんは家庭の事情によって生後三日目から高校卒業までの十八年間を「乳児院」と「児童養護施設」で育ちました。
道場の若竹学園や亀山学園も同じですが、日曜祭日には親が迎えに来て自宅に帰れる児童と、諸事情から全く帰れない児童がいます。全員が帰宅しないのであればそれなりの納得もできるでしょうが、帰れない児童の心は寂しさとやるせなさで自制心さえ失って先生やモノにあたってしまうこともあります。
吉夫さんは「もしや今日は迎えに来てくれるのでは…」と、駅が見える学園裏の丘に上がって眺めていたそうです。眺めてはいましたが、生まれてこの方一度も会ったことのない母なので顔も分かりません。吉夫さんは自分の母の顔をマリア様の顔と同じだ、と長く信じていたそうです。
中学一年生の頃に「母に会いたい…」と言って職員を困らせたそうですが、本人には全く記憶がないそうです。何をしても消極的にとらえてしまう毎日の生活の中で、習字の先生に字を褒められたそうです。そのことがとても嬉しくて一生懸命に練習したそうです。練習を重ねれば上達して当然で、上達するからまた褒められる、と言うプラスの相乗効果が働いたようです。
市長に就任してからは、市長名で出す賞状のあて名はどんなに忙しくても市長自身が書いているのも、先生に褒められたのが契機だった、と話していました。
吉夫さんがマイナス発想からプラス発想に転じられたのは、「師」と仰げる方との出逢いがあったからだそうです。その方は吉夫さんが入所している児童養護施設を運営している法人の理事長先生であり日蓮宗のご住職だったそうです。
その方から高校時代に「福祉とは自己実現すること」と教わり、大学に入っては東北福祉大の萩野浩基学長より「福祉とは人間をどう捉えるかだ。突き詰めると自分自身をどう捉えるかが福祉である」と教わり、自分のゆるぎない福祉観の礎となっていると言っています。
人が人になるには全面的に信頼できる人との出逢いが必要です。華厳教に出てくる求道の善財童子は五十三人の善知識を歴訪して様々な教えを学び菩薩の位に達したと言われています。
因みにこの故事から東海道五十三次が命名されたと聞いています。
四月に開所した四恩の里本部運営の自立援助ホーム「なごみハウス圓」は、児童養護施設の在所期間が切れる十八才前後の帰宅場所のない少年を受け入れて自立と就業に導く施設です。
A子ちゃんは産まれて直ぐに乳児院引き取られ、以後十八才まで児童養護施設で育ちました。彼女が言いました「私なんか、生まれてこなかったほうがよかった…」と。その時私は何も答えることが出来ませんでした
高萩市の草間吉夫市長さからサインしてもらった著書を渡して熱く語りかけたいと思います。
―大燈記―
 自分に自信を持とうよ
自分に自信を持とうよ